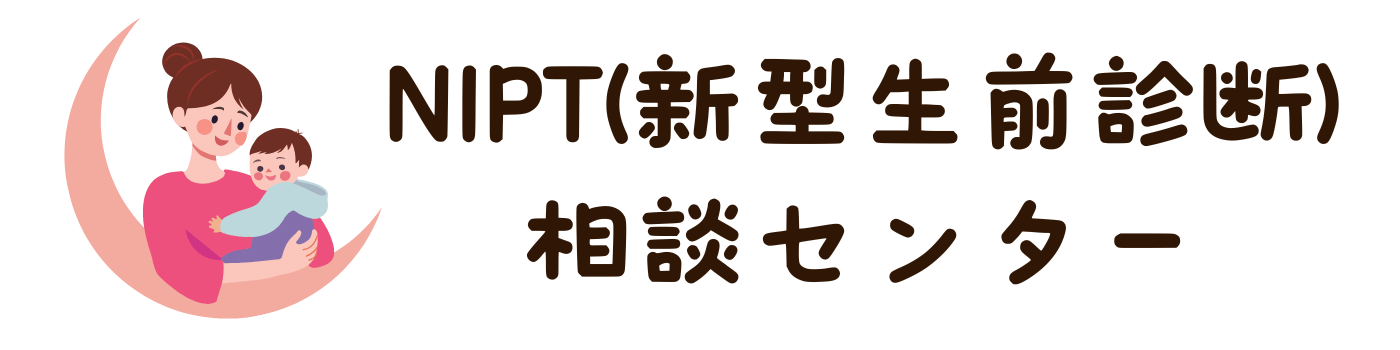NIPT検査(新型出生前診断)とは、妊婦さんの血液を採取するだけで、赤ちゃんの染色体異常の可能性を調べることができる最新の検査方法です。
この検査は10週〜22週の妊婦さんが受けることができ、特に21トリソミー(ダウン症)については99.1%という高い検出率を持つことが特徴です。
本記事では、NIPT検査の特徴から検査結果の見方、そして検査を受ける際の注意点まで、誰にでもわかりやすく解説していきます。
NIPT検査とはなにか?基本情報と特徴を解説
NIPT検査の特徴と対象者
NIPTは、妊婦さんの血液から赤ちゃんの染色体異常の可能性を調べることができる非侵襲的な出生前診断です。この検査は妊娠10週から受けることができ、お腹の赤ちゃんに直接触れることなく安全に実施できます。
妊婦さんの腕から採血するだけの簡単な検査ですが、その精度は従来の検査と比べて非常に高いことが特徴です。主な対象者は35歳以上の高年齢妊婦さんですが、それ以外にも染色体異常の子どもを出産した経験がある方や、超音波検査で異常が疑われる方なども検査の対象となります。
また、不安が強い方であれば年齢に関係なく受検することも可能です。検査結果は採血から1-2週間程度で判定され、陽性・陰性・判定保留のいずれかで通知されます。
検査でわかる疾患の種類
NIPTは、赤ちゃんの染色体に関する3つの代表的な疾患について調べることができます。調べられるのは、ダウン症候群、エドワーズ症候群、パトウ症候群と呼ばれる疾患です。
この検査は、母体から採血するだけで高い精度で調べられますが、確定的な診断ではありません。検査結果で疾患の可能性が示された場合(陽性の場合)は、確実に診断するために羊水検査などの追加検査が必要です。
また、赤ちゃんが生まれつき持つ可能性のある病気は他にもたくさんあり、NIPTだけですべての病気が分かるわけではありません。そのため、定期的な妊婦健診での超音波検査なども含めて、総合的に赤ちゃんの健康状態を確認していくことが大切です。
| 染色体異常 | 感度(検出率) | 特異度 | 有病率(中央値) | 陽性的中率 |
|---|---|---|---|---|
| Trisomy 21 | 99.6% | 99.97% | 1.25% | 97.5% |
| Trisomy 18 | 99.2% | 99.95% | 0.60% | 91.8% |
| Trisomy 13 | 100% | 99.91% | 0.12% | 58.0% |
検査費用と保険適用について
NIPT検査は保険適用外の自費診療となっており、医療機関によって費用は異なります。一般的な費用の相場は10万円から25万円程度で、これには検査前の遺伝カウンセリング料金も含まれています。
高額な検査ではありますが、より安全で精度の高い検査方法として多くの方に選ばれています。医療機関によっては分割払いや、陽性だった場合の確定検査費用の補助制度を設けているところもあります。
また、検査前には必ず専門医による遺伝カウンセリングを受ける必要があり、この費用も含めて検討する必要があります。検査を検討する際は、複数の医療機関の料金体系や支払い方法を比較検討することをおすすめします。
NIPT検査でわかる染色体異常について
21トリソミー(ダウン症)の特徴と発症率
21番染色体が通常の2本ではなく3本存在する状態がダウン症候群です。発症率は出産時の母体年齢が大きく関係しており、20歳では約2,000人に1人程度ですが、40歳では約100人に1人と高くなります。
この染色体異常がある場合、赤ちゃんには特徴的な身体的特徴が現れることがあります。発達の遅れや運動機能の発達に影響が出る可能性がありますが、その程度には個人差が大きく、適切な療育支援により多くの方が学校生活や社会生活を送ることができます。
また、約半数に心臓の異常が見られ、その他に甲状腺疾患や消化器系の合併症を伴うことがありますが、現代の医療技術の進歩により多くの症状に対して効果的な治療が可能になっています。平均寿命は50〜60歳と言われており、早期発見による適切な医療ケアと支援体制の整備が重要になっています。
| 母体年齢 | 発症率 |
|---|---|
| 20歳 | 1/2,000 |
| 35歳 | 1/350 |
| 40歳 | 1/100 |
18トリソミー(エドワーズ症候群)の特徴と発症率
18番染色体が3本存在するエドワーズ症候群は、約3,500〜8,500人に1人の割合で確認される染色体異常です。この症候群の特徴として、胎児期からの重度な発育不全が見られ、出生できた場合でも低体重出生となるケースが多く見られます。
また、顎が小さい、後頭部の突出、両眼隔離、手指の重なりや手足の拘縮といった身体的な特徴が現れやすく、心臓病の発生頻度が非常に高いことが知られています。
生命予後は厳しく、多くは妊娠経過中に流産や死産となり、出生した場合でも生後2ヶ月までに半数が亡くなり、1年生存率は10〜30%程度とされています。小児慢性特定疾病に認定されており、手厚いサポート体制が整備されています。
13トリソミー(パトウ症候群)の特徴と発症率
13番染色体が3本存在するパトウ症候群は、約5,000〜12,000人に1人の割合で発生する染色体異常です。この症候群の特徴として、口唇口蓋裂や多指症などの外表的な合併症の割合が他のトリソミーと比較して高く、運動機能や知的発達に関連する神経系の発達に重度の遅れが見られます。
多くの場合、心臓や脳、消化器系に複数の合併症を伴い、生命予後は非常に厳しいとされています。約50%は妊娠中に流産や死産となり、出生した場合でも生後1年での生存率は5〜10%程度です。
13トリソミーの一部には、染色体が3本でなく部分的に混じっているモザイク型という症例もあり、この場合は症状がやや軽くなる可能性があることが知られています。
NIPT検査の精度と判定について
検査結果の種類と解釈方法
NIPT検査の結果は陰性・陽性・判定保留の3種類で判定されます。陰性の場合は染色体異常の可能性が極めて低いことを示していますが、完全に否定するものではありません。
陽性の場合は染色体異常の可能性が高いことを意味しますが、これも確定診断ではないため、必ず羊水検査や絨毛検査などの確定検査が必要になります。
検査の精度は特に21トリソミー(ダウン症)において高く、検出率は99.1%と報告されています。ただし、18トリソミーや13トリソミーについては、それぞれ若干低い検出率となっています。検査結果は通常、採血から1-2週間程度で判定され、担当医から詳しい説明を受けることができます。
| 判定結果 | 意味 | 次のステップ |
|---|---|---|
| 陰性 | 異常の可能性が低い | 通常の妊婦健診継続 |
| 陽性 | 異常の可能性が高い | 確定検査が必要 |
| 判定保留 | 判定不可能 | 再検査の検討 |
偽陽性・偽陰性について
偽陽性とは、実際には染色体異常がないにもかかわらず、検査結果が陽性となる場合を指します。特にダウン症の場合、偽陽性率は約2.7%(約37人に1人)とされており、他の染色体異常ではさらに高くなる傾向があります。
一方、偽陰性は検査で陰性と判定されたにもかかわらず、実際には染色体異常がある場合を指し、その確率は約0.01%(約10,000人に1人)とされています。
これらの誤判定が生じる理由としては、胎盤のモザイク(正常な細胞と異常な細胞が混在している状態)や、母体側の染色体異常、検査時の技術的な要因などが考えられます。このような可能性があるため、検査結果の解釈には慎重な判断が必要とされています。
判定保留になるケースとその対応
判定保留は検査結果を確定できない場合に生じ、全体の約0.3〜0.4%で発生します。主な原因として、母体血液中の胎児DNAの量が不足している場合や、母体のBMIが高い場合、また胎盤モザイクの存在などが挙げられます。
判定保留となった場合の対応としては、再度NIPTを実施する、羊水検査などの確定検査に進む、あるいはNIPT検査自体を断念するという選択肢があります。
特にBMIが高い妊婦さんの場合は、検査が不能となるリスクが高いため、事前に担当医と十分な相談が推奨されています。なお、再検査を選択する場合は、ある程度の期間をおいてDNA量が増加するのを待つことで、判定可能となるケースもあります。
NIPT検査を受ける時の注意点
検査時期の選び方は?
NIPT検査は妊娠10週から16週の間が最適な検査時期とされています。この時期を選ぶ理由は、母体血液中の胎児DNAが十分に存在し、より正確な検査結果が得られるためです。
ただし、クリニックによっては初期の超音波検査(胎児ドック)を実施してからNIPT検査を行うことを推奨しており、その場合は11週以降の実施となることが一般的です。
検査時期が早すぎると胎児DNAが少なく判定保留となるリスクが高まり、逆に遅すぎると確定検査や今後の治療方針を決める時間が限られてしまう可能性があります。また、胎児の状態を総合的に判断するためには、NIPTと合わせて超音波検査なども実施することが推奨されています。
| 妊娠週数 | 検査の特徴 |
|---|---|
| 10-11週 | 早期発見可能だが判定保留のリスクあり |
| 11-14週 | 最も推奨される時期 |
| 15-16週 | 確定検査の時間を考慮する必要あり |
事前カウンセリングは大事
NIPT検査を受ける前には、必ず遺伝カウンセリングを受ける必要があります。これは単なる手続きではなく、検査の特徴や限界、結果の解釈方法、確定検査の必要性などについて十分な理解を得るための重要なステップです。カウンセリングでは、臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーが、個々の状況に応じて丁寧な説明を行います。
特に検査結果が陽性だった場合の心理的な影響や、その後の選択肢について事前に理解を深めることが大切です。また、検査を受けない選択肢についても話し合われ、夫婦で十分に検討する時間を持つことができます。カウンセリングは対面だけでなく、オンラインで実施される場合もあり、より柔軟な相談機会が提供されています。
確定検査が必要なケースは?
NIPTで陽性結果が出た場合には、必ず確定検査を受ける必要があります。確定検査には主に羊水検査と絨毛検査の2種類があり、どちらの検査を選択するかは妊娠週数や個々の状況によって判断されます。羊水検査は妊娠15週以降、絨毛検査は妊娠11-14週で実施可能です。
これらの検査では、胎児の細胞を直接採取して染色体分析を行うため、より正確な診断が可能になります。ただし、これらの確定検査には約0.3%(羊水検査)から1%(絨毛検査)程度の流産リスクが伴うため、検査の実施については慎重な判断が必要です。
また、確定検査の結果が出るまでには数日から1週間程度かかることも考慮に入れる必要があります。